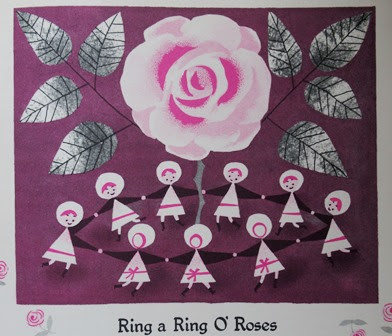「moat モート」とは、城郭や市外壁を囲む、多くは水を湛えた人工の堀の事です。元々は軍事防衛の機能として築かれましたが、後にイギリスでは金持ちのステイタスでもあるかのように、大きなお屋敷の庭園形式、すなわち装飾品の一つとして、邸宅の周囲にも設けられるようになりました。それ故、モートはイギリスの結構至る所に今でも残っています。数年前にとある国会議員が、自宅のモートに住む鴨の餌代まで、議員活動費用として政府に請求していたのが問題になりました(何処の国にもお粗末な政治家は居るもんだ…)。
私が住んでいる町にも、あちこちに幾つかモートが残っています。それらは元マナーハウス(荘園館)や司祭館、豪邸のモートで、中には未だお屋敷が現存し実際に人が住んでいる場合もあります。
其処へ行くには公共遊歩道が続いていて、入り口にはいつの間にイングリッシュ・ヘリテイジと地方自治体管理の看板が建てられていました。
大きな広葉樹に囲まれた遊歩道で、落ち葉の絨毯が凄い厚み。落ち葉の量は自然の豊かさの象徴のように見えますが、多過ぎても問題で、イギリスでは毎年線路に積もって列車の遅延や欠行を引き起こします。
これらの巨大な樹木は、多分ここに住宅地が築かれる前から存在している原生林の名残りで、宅地開発後もそのまま合間に残している物と思われます。
モートに到着。ここのモートは典型的な四角形、つまりロの字型のモートです。
多くの部分は、幾つかの個人の裏庭に面して囲まれています。以前は、モートに小舟を浮かべている家も見掛けました。一見優雅そうですが、湿気や洪水、蚊の発生等のリスクも多いと思います。防衛の為でもないのに家の周りに水堀を築くなんて、湿気の多い日本では在り得ない発想です。
このモートは、誰がいつの時代に何の為に築いたのか、未だ解明されていないそうです。
モートに囲まれた中島は、今は高い樹木に覆われているのみ。ここへ通じる、橋のような物も存在しないようです。恐らくこの中島に建造物の痕跡が何も見当たらない為、何の目的で築かれたのか謎のままなのだと思います。
日本の古墳は結界として堀で囲まれている場合もあるので、もしかして埋葬地だったのかも…とか想像してみたり。確か故ダイアナ妃の墓所が、スペンサー伯爵家領内の湖の中島に在ると言うのを思い出しました。
モート用の遊歩道と言えど、実際にモートの姿が見えるのは、木々の合間から僅かに二箇所のみです。以前はほとんど一周近く歩けるようになっていたように記憶していますが、試しにこのモートの反対側の住宅地へ行ってみたら、遊歩道のような通路は扉で閉鎖されていました。
周囲は、築造年は古くないものの、大きなデタッチド・ハウス(完全一戸建て)の多いお屋敷街になっています。
それにしても、うちの御近所の種類に乏しい彩のショボい紅葉でさえ、天気が良いだけで映えるなあと実感。
距離的にも治安的も自然の豊かさでも、日常の運動としては理想的な散歩コースです。