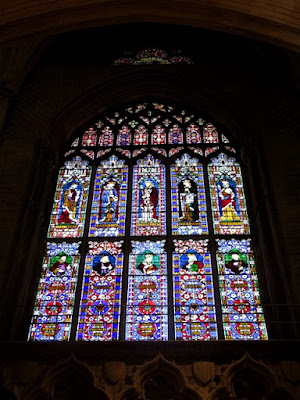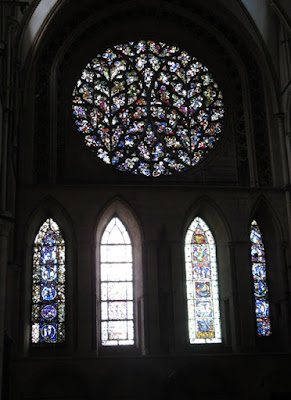以前モンスター・ハイのフランキー人形をリペイントしたら、着物が似合いそうな顔に仕上がったので、やはり一度和装をさせてみたいと思っていました。しかし何せ闇より出でて闇より黒い怪物人形だから、絶対に一筋縄の着物の着こなしでは収まりそうもありません。目指したのは、一応夜の桜の精の妖姫です。
桜柄の和風プリント生地の中でも、ピンク地なので最も桜を簡単にイメージさせる為、今まで何度もドール服として登場した布を使用しました。ruruko用には一度振袖を縫いましたが、同じ布でもっと大きなサイズのドール用の振袖があっても良いだろうと思い制作。
しかし着物が概ね仕上がった時、実際にこの人形に試着させて見て、イッパツでこりゃ駄目だ!!と言う事に気付きました。体型&可動域が根本的に着物に不向きで、着物を真っ当に着こなせないのです。
上半身が異様に華奢な体型は、補正で何とかなるのかも知れませんが、向かって左腕は曲がったままの上、手の甲が大き過ぎて腰に引っ掛かり腕を後方に回す事が出来ず、着物に袖を通すのだけでも一苦労です。そもそも腕が短く両腕を広げられないボディなので、袖を正面に向ける事すら出来ません。
膝の関節は曲がる仕様になっていますが、着物の場合、どちらかと言うとこの和顔バービーのように、例え脚は全く曲がらない固定式でも、肘や手首の関節の曲がるドールのほうが、ポーズのバリエーションを出し易くて扱い易いと思いました。
返って、こんな全く正統派の着物の着こなしじゃないお引きずりだから、未だ誤魔化せているのかも。着物のピンク色が明るい為に闇深さは感じられませんが、デザイン的には彼女に悪くないと思っています。
ペットワークスからかつて発売されたCCS 18SS momokoの、お引きずり姿を参考にしました。そのテーマは「エッジな成人式スタイル」らしいのですが、エッジが利き過ぎてまるでガイジンが考えた着物のようなえっち臭い着こなしで、あんな遊女みたいな格好で成人式に参列したら、親は泣くし周囲もドン引きすると思いますよ(笑)。
しかし後からペットワークスのCCS 18SS momoko DSで確認すると、そのお引きずりの着物は、実は元の構造からして本式の着物の造りとは大きく違う、ウェスト切り替えのある最初から衣紋が大きく抜かれた、どちらかと言うと洋服に近い状態になっていました。一方この着物は、おはしょりを上げてきちんと帯を結ぶと、一応普通に振袖として着付ける事も出来ます。
ちりめんの桜の髪飾りは、昔母が送ってくれた携帯ストラップでした。ストラップとしては今までも今後も絶対に使う事はないものの、こうして無駄になる事なくドールには役立っています。
桜の花って、元々それ用として作られていない限り、造花で表現するのが中々難しい。帯飾りの中心は、デイジーだった造花の花びらの先をピンキング鋏でカットし、重ねて八重桜っぽく見せたつもりの苦肉の策です。
最近玩具店を覗いたら、モンハイの新商品が並んでいました。マテルのライバル社MGAの「レインボー・ハイ」が子供にも大人にも人気を博している為、マテルがそれに対抗するには、かつて一世風靡を起こしたモンハイを再登場させるしかなかったのかも知れません。ファッション・ドールのシェアでは、今でもバービー人形が一番人気だと思いますし、実際売り場面積的にも最大ですが、大人コレクター向けを除いては、どうも商品としての新鮮さやインパクトが薄い印象です。今モンハイが販売されていると言う事は、私にとっては4、5年後にはその中古がまた多く出回ると言う事です。「クリエイタブル・ワールド」や「シンディ・プレイ」の中古人形も、早く手に入らないかと心待ちしている私です(笑)。